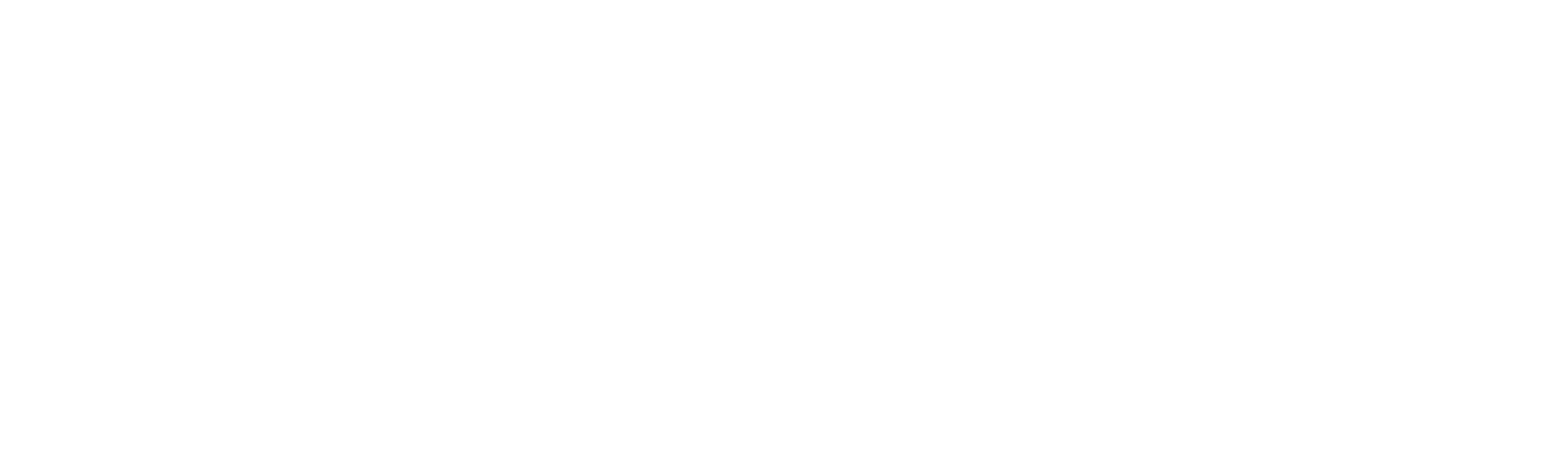「就活の軸ってどうして必要なの?」
「就活の軸を決めるにあたっての考え方を知りたい!」
「就活の軸にはどのような役割があるのかを知りたい!」
この記事は
①就活の軸 考え方編
②就活の軸 決め方編
③就活の軸 答え方編
の3つがある中で、「就活の軸の“考え方”」について書いています。
就活では「就活の軸」の作成が必要不可欠です。
しかし、そもそも就活の軸がどういうものなのかを知っていないと、正しく作れなかったり、作れても上手く答えられません。
この記事では、就活の軸の「考え方」を徹底的に解説し、これから就活の軸を作っていく方や見直す方のお悩みを解消します。
ぜひ最後までご覧ください。

目次
就活の軸とは?
そもそも就活の軸とは、
「入社をする上で譲れない条件」
「入社をする上で譲れない価値観」
のことです。
就活では「企業選び」をする必要があり、そのための判断軸が「就活の軸」です。
例えば、キャリアアンカーでインタビューしたある先輩社員は、以下の3つの就活の軸を掲げていました。
・大企業である
・業界や会社が伸びている
・その会社の人と働きたいと思える
このように、企業を絞り込むための判断軸が就活の軸であり、複数の軸を持つことで、より自分に合った企業を見つけることができます。
「もっと先輩社員の就活の軸を知りたい!」
そう思った方は、こちらの記事をご覧ください!
【50選+5具体例】OBが掲げていた就活の軸の実例から解答例までを一覧で大公開!

就活における“就活の軸”の立ち位置
就活の軸がどのようなものか、大まかなイメージが掴めたと思います。
ここからは、就活の全体像を見た上で、就活において就活の軸が必要な理由を理解しましょう。
以下の図は、大まかな就職活動の流れです。

就活の軸の「流れ」をより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください⇩
【26卒必見!】就活は何から始める?スケジュール付きで完全解説
このように、「企業の絞り込み」と「選考の突破」において、就活の軸は必要になってきます。
更に、この2つのフェーズはそれぞれ次のように捉えることができます。
「企業の絞り込み」 → 就活生の目線
「選考の突破」 → 面接官の目線
次項では、2つのフェーズにおいて就活の軸が必要な理由を
就活生の目線
面接官の目線
に沿ってお伝えします。

就活の軸が必要な理由①:就活生の目線
企業を絞り込むために必要
就活は、”限られた時間の中で、沢山ある企業から自分に合う1社を見つける過程”です。
日本にある企業の数は、およそ360万社です。
可能ならば1社1社丁寧に見た上で入社する企業を見極めたいところですが、現実的ではありません。
そこで、就活の軸を持つことで、自分に合った企業を効率的に絞り込むことができます。
例えば、「年収1000万円以上」という就活の軸を持っているとき、大量の企業の中から「年収1000万円以上」の企業がリストアップされます。
しかし、これだけでは業界も職種も企業規模もバラバラで、志望企業は全く選べません。
そこで、「年収1000万円以上」のほかに、
『ITに関わる仕事がしたい』
『ワークライフバランスを大切にしたい』
などの軸を足していくことで、自分の軸に合った企業を絞り込むことができます。
また、就活の軸を作る際は、本音をベースに設定していきましょう。
自分の本音と向き合った質の高い就活の軸ほど、入社後のミスマッチが起こりにくくなります。
企業を絞り込む具体例
キャリアアンカーでインタビューしたとある先輩社員は、以下の3つの軸を掲げていました。
・事業を伸ばすことを学べるか
・尊敬できる人がいるか
・コミュニケーションコストが低いか
彼は「事業を伸ばすことを学べるか」といった軸を元に、「コンサル」と「ベンチャー」に方向性を絞りました。
その後、社員の方とコミュニケーションを取る中で、残り2軸が最も満たされた「コンサル」に絞っていったそうです。
このように、就活の軸を複数設定しておくことで、企業を絞り込むための判断軸が、就活の軸です。
面接官はその就活の軸を聞くことで、就活生の志望度を探っています。
Kさんのインタビューはこちらから!
コンサルって何するの?現役コンサルタントが語る”泥臭い仕事内容”

就活の軸が必要な理由②:面接官の目線
選考を突破するために必要
学生が企業選びをする一方で、面接官は”就活生選び”を行っています。
というのも、就活生だけでも毎年40万人以上おり、採用人数に対して、多い企業では数百倍もの就活生がエントリーします。
その中から自社に合う一握りの人材を選ぶために、選考というフィルターにかけるのです。
選考では、あらゆる質問を通して、あなたが
を判別します。
その質問の一部として、「就活の軸」は必ずと言っていいほど聞かれます。
このように、
就活生にとっての企業選びだけでなく、企業にとっての採用活動でも、就活の軸は必要なのです。
就活の軸を通して見られるポイント
就活の軸を通して、具体的に面接官が見ているポイントは2つあります。
これらを見極めるために、実際の面接では、下記のような質問を投げかけられます。
・就活の軸は何ですか?
・なぜその就活の軸にしたのですか?
・軸が自社とマッチするかをどのように判断しますか?
面接に通過する就活の軸の答え方を詳しく知りたい方は、
こちらをご覧ください⇩
二度と就活の軸の答え方には困らない!例文付きで回答の仕方を徹底解説【就活の軸完全攻略編③】

就活の軸の「考え方」に関する注意点
就活の軸は手段に過ぎない
就活のゴールは、あなたに合ったたった1社の企業に入社することです。
就活の軸を持つことは、そんな就活を効率的に進めるための手段に過ぎません。
就活の軸が完璧にできたら、その軸を使ってあなたにあった企業を絞り込み、その企業の選考を突破できるよう、対策をしていきましょう。
就活の軸は途中で変えてもいい
説明会やインターン、選考に参加する中で、業界や企業への印象が変わることがあります。
就活をする中で就活の軸が変わったとしても、特に問題はありません。
例えば、あなたが「市場価値を高めたい」という軸を持って就活を進めているとしましょう。
軸に基づいて、IT業界、コンサルティング業界、人材業界を見ていましたが、特にIT業界に魅力を感じました。
そのような時は、
「市場価値を高めたい」→「ITの力で市場価値を高めたい」
のように、軸を変えてしまって良いのです。
選考の中で、就活状況や就活の軸の変遷を聞かれることがあるので、
「なぜ変わったのか?」
「変わった上で、なぜその企業を受けるのか?」
などをしっかり言語化しておきましょう。
どこにも当てはまる軸は避ける
就活の軸の目的の1つは「企業を絞り込むこと」でした。
しかし、どこにでも当てはまる軸では、なかなか企業を絞り込むことができません。
例えば、「社会貢献がしたい」という軸は、一見すると良い軸に思えます。
しかし、どの企業でも社会に対して何らかの価値を提供しているので、極論全ての企業が社会貢献をしていると言えます。
このような場合は、あなたが実現したい「社会貢献」をより具体的に言語化しましょう。
「社会貢献」の具体例
・社会課題を解決して、社会貢献がしたい
・生活インフラを提供して、社会貢献がしたい
・世の中に無い新たな価値を創って、社会貢献がしたい
原体験に紐づいた就活の軸にする
就活では「自分がどういう人間なのか」を企業に伝えるために、エピソードの「一貫性」が重要です。
就活の軸に関しても、選考の中で「原体験」「志望動機」「就活状況」などと併せて、一貫性があるかを見られます。
しかし、何となくで設定した就活の軸では、あなた自身との結びつきが弱く、選考で見透かされる可能性が高いです。
しっかりと自己分析を行い、原体験やあなた自身が持つ根源的な価値観に紐づく軸を設定しましょう。

就活の軸の考え方が理解できた方へ
この記事では、「就活の軸とはどのようなものか」について徹底的にご説明しました。
就活の軸の「考え方」が理解できたら、
次はあなた自身の就活の軸を「決める」フェーズです。
下の記事では、就活の軸の「決め方」について徹底解説しているので、ぜひご覧ください!
たったの4ステップ!簡単に真似できる就活の軸の決め方【就活の軸完全攻略編②】
たったの4ステップ!簡単に真似できる就活の軸の決め方【就活の軸完全攻略編②】